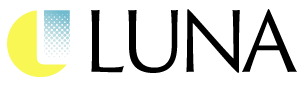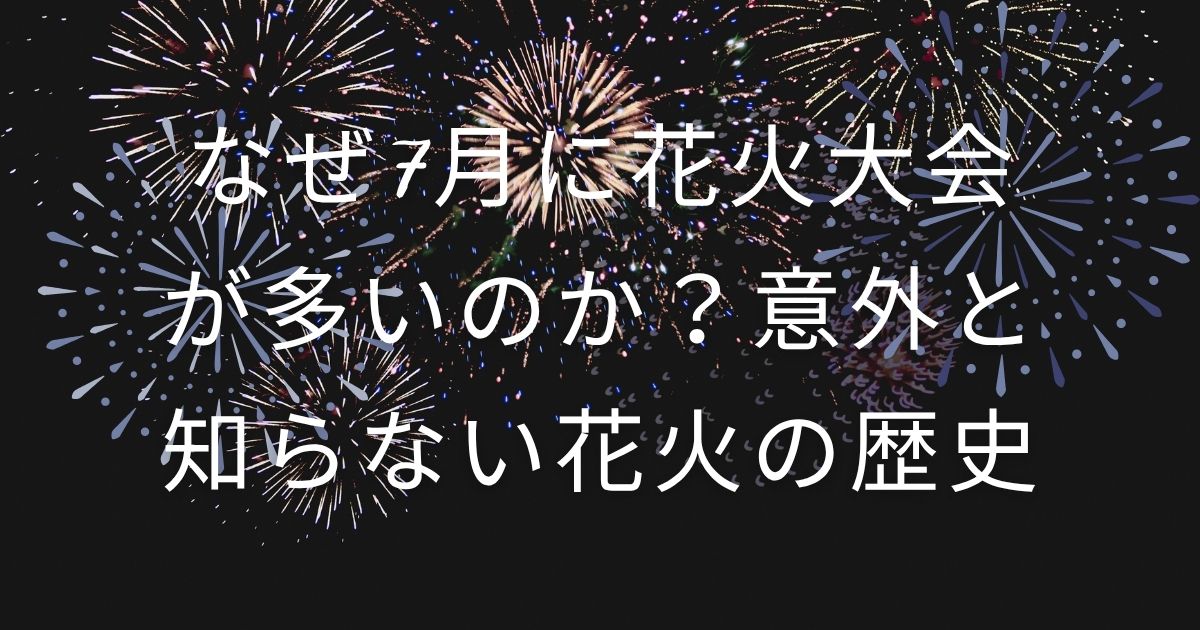皆さん、こんにちは!N.Tです。
夏といえば何を思い浮かべますか?
海、かき氷、セミの声…そしてやっぱり花火大会!
7月に入ると、全国各地で花火大会の情報が増えてきますよね。
でもふと思ったんです。
「なんで花火って、7月に集中してるんだろう?」
というわけで、ちょっと調べてみました!
🎇花火大会が“夏の風物詩”になった理由
そもそも花火は、室町時代に火薬と一緒に日本に伝わったと言われています。
当時は“武士の娯楽”や“軍事技術”の一環だったとか。
江戸時代に入ると、少しずつ庶民にも広がり、
1733年、隅田川で行われた「川開きの花火」が、日本初の本格的な花火大会とされています。
なぜ7月に多いの?
理由はいくつかありますが、主に以下の3つが大きな要因です
① 暑すぎず、梅雨明けで天気が安定する
→ 特に本州では7月中旬〜下旬が梅雨明けのタイミング。
湿気も少し落ち着き、夜空が見えやすい時期になります。
② お盆前に行う“弔い”の意味合い
→ 江戸時代の「川開き」も、実はお盆前の供養行事がルーツ。
今でも“夏の夜に故人を偲ぶ”という意味で開催される地域も。
③ 観光・経済効果が高まる夏の集客シーズン
→ 夏休み・三連休・海の日などの祝日もあり、人が集まりやすいタイミングというのも、実務的な理由の一つですね!
✍️まとめ:花火は“美しさ”+“歴史”の融合
今では夏のレジャーの定番となった花火ですが、
もともとは祈りや供養の意味を持ったものでした。
歴史に思いをはせながら、空を見上げてみるのもいいかもしれませんね🎇
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
それでは、また次回のブログでお会いしましょう!